-
最近の投稿
アーカイブ
カテゴリー
投稿日カレンダー
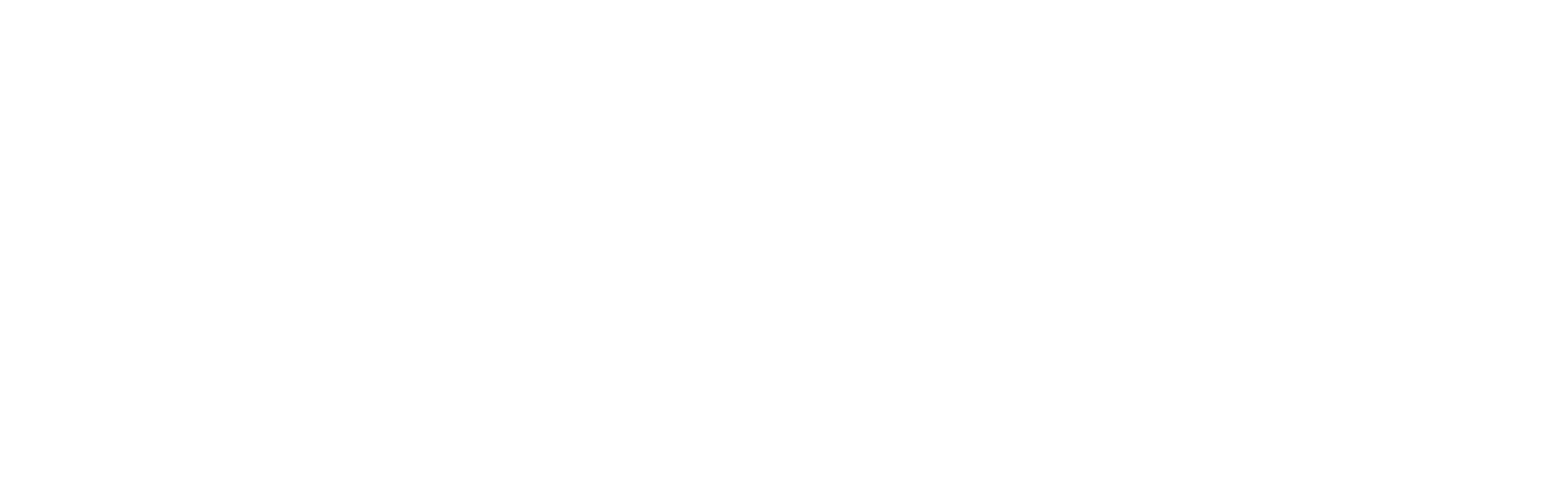
皆さんこんにちは!
金色、更新担当の中西です。
本日は第4回水炊き雑学講座!
今回は、人気のブランド鶏についてです
日本には数多くのブランド鶏が存在し、それぞれの品種には独自の飼育方法や味の特徴があります。特に「地鶏」と呼ばれる鶏は、特定の条件を満たした品種であり、一般的なブロイラー(短期間で成長させる鶏)とは異なる歯ごたえや旨味を持っています。
日本のブランド鶏は、大きく以下の3つに分類されます。
地鶏(じどり)
銘柄鶏(めいがらどり)
ブロイラー
この中でも、「地鶏」と「銘柄鶏」がブランド鶏として知られています。
日本には、多くのブランド鶏が存在し、それぞれが独自の特徴と歴史を持っています。
ブランド鶏は、それぞれの地域の風土や伝統に支えられながら、最高の食材として育てられています。鶏肉好きの方は、ぜひ地域ごとの味の違いを楽しんでみてください!
![]()
皆さんこんにちは!
金色、更新担当の中西です。
本日は第3回水炊き雑学講座!
今回は、歴史についてです
水炊きは、鶏肉をじっくりと煮込んで旨味を引き出す鍋料理であり、日本の食文化の中でも特に歴史が深い一品です。福岡・博多を代表する郷土料理として知られていますが、全国的にも親しまれており、シンプルながら奥深い味わいが特徴です。
水炊きの起源を探ると、中国の火鍋や関西の「鶏鍋」の影響を受けながら、日本独自の進化を遂げた料理であることが分かります。本記事では、鶏の水炊きの歴史やその背景、全国の水炊き文化の違い、現代の水炊きの進化について深く掘り下げていきます。
鍋料理の歴史は非常に古く、中国の火鍋(フォンゴ)がその起源とされています。
中国の火鍋(紀元前~唐時代)
日本への伝来(奈良~平安時代)
しかし、この時点では「鶏肉」をメインにした水炊きはまだ誕生していませんでした。
日本では、室町時代から鶏肉を使った鍋料理が少しずつ登場していきます。
室町時代(14~16世紀)
江戸時代(17~19世紀)
この頃の鍋料理は、味噌や醤油をベースにした「すき焼き風」の味付けが主流でした。しかし、のちに福岡で独自の進化を遂げ、「水炊き」として確立されていきます。
現代の水炊きのスタイルを確立したのは、明治時代(1868~1912年)の福岡・博多とされています。
中国・長崎の「白湯スープ」の影響
博多独自のスタイルが確立
当時の博多は、水炊きを「宴会料理」として提供する店が増え、庶民にも広まっていったとされています。
昭和時代になると、博多の水炊きが東京や大阪にも広まり、全国的に知られるようになりました。
水炊き専門店の登場(戦後復興期)
家庭料理としての定着(1960~70年代)
この頃から、水炊きは「特別な料理」から「家庭でも楽しめる料理」へと変化していきました。
現代では、さまざまなアレンジ水炊きが登場し、より幅広い層に楽しまれています。
日本の食文化のグローバル化とともに、水炊きは海外でも注目を集める料理となりました。
水炊きは、中国の鍋文化や日本の鶏鍋文化をルーツに持ち、明治時代の福岡・博多で独自に発展した料理です。
これからも水炊きは、伝統を守りながら新しい形へと進化し、日本の食文化を支え続けていくでしょう。
![]()